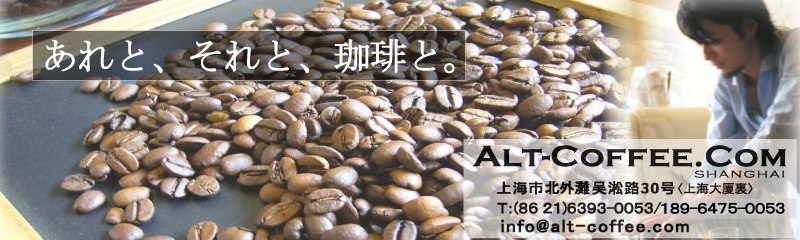|
コーヒーの好み、方程式でピタリ 金沢学院大・廣瀬教授確立
金沢学院大知的戦略本部長で日本コーヒー文化学会副会長の廣瀬幸雄教授は三日までに、国内の約二千人が舌で感じた味を分析し、コーヒーの好みを客観的に算出する方程式を確立した。この式を活用すれば、飲む人が香りや味など十四項目をチェックするだけで、豆の種類はもちろん、採れた斜面の日当たりやいれ方、焙煎後に何日目の豆が好きかなど、飲む人の細かな好みにぴたりと合わせた「オーダーメード」の味を数字ではじき出せる。
コーヒーの味を科学的・客観的に分析する方法として、これまではコーヒーそのものの成分分析が行われてきた。しかし、コーヒーの味の因子となる成分は約八百あると言われており、どの因子がどの味を決めるか、解明されていない。こうした現状を受け、廣瀬教授は発想を転換。飲み手の好みを分析してコーヒーの味を割り出す方程式を作る研究を進めてきた。
廣瀬教授は二〇〇二(平成十四)年から五年間、全国で約四百回開いたコーヒー講座の二千人を超す受講生に、ケニアやコロンビアなど六種類の豆でいれたコーヒーを飲んでもらい、香りや味、コクなど五項目について記入式のアンケート調査を実施した。
この結果を多変量解析し、甘みや酸味、苦みといった味と、性別や年齢、地域などとの相関関係を解明。この関係に基づく十四項目を決め、「濃さ」「甘い香り」などのコーヒーの特徴を表す説明変数(x)に「とても」「まあまあ」などの飲み手の好き嫌いの度合い(a)をかけて合算したものに、飲み手の知識や経験などの「コーヒー力」(b)を加えたものが「好み」であるという方程式を確立した。
この式で計算したところ、平均的な日本人がコーヒーに求めるものはコクとキレで、香りや味は二の次であることが分かった。
廣瀬教授は「この式を使えば、好みにぴったりのコーヒーを味わえる。今後もできるだけ多くの好みのデータを集め、より信頼性のおける式にしたい」と話している。
http://www.hokkoku.co.jp/_today/H20080104104.htm
これは特に目新しい試みではなく、
良いお店では昔から当たり前のように行われていることなんですけどねw
|